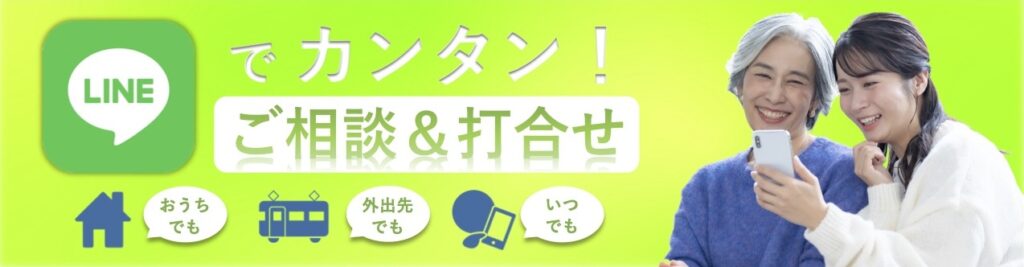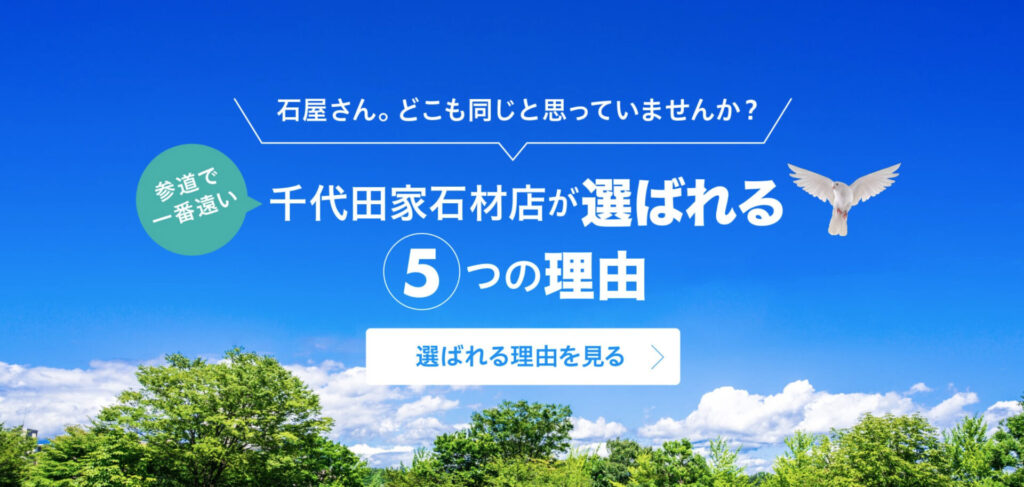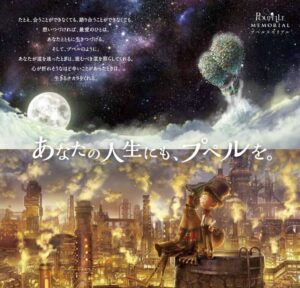納骨の手続きから当日の流れまで|必要書類・準備・服装マナーについてご紹介

納骨とは、火葬を終えたあとにご遺骨をお墓や納骨堂に安置する大切な儀式のことをいいます。
ご家族や親しい方々が集まり、故人を偲びながら手を合わせるひとときは、悲しみを分かち合い、心を落ち着ける大切な時間でもあります。日本の供養文化において、納骨はご葬儀と並んで欠かすことのできない節目の行事といえるでしょう。
ただ、「納骨はどこに連絡をすればいいの?」「どんな書類が必要なの?」といった具体的な流れや準備については、実際に経験してみないと分かりにくいものです。特に初めて納骨を迎える方にとっては、不安や疑問が多くて当然です。
そこで今回の記事では、納骨の基本的な流れや必要な書類、供えるお花やお供物について、分かりやすく丁寧にご紹介します。また、石材店がどのようにお手伝いできるのかもあわせてお伝えします。
少しでも「納骨のことが理解できて安心した」と感じていただければ幸いです。
○納骨とは?基本の意味と役割
・納骨とはなにか
納骨とは、火葬を終えたあとに残されたご遺骨を、お墓や納骨堂に安置する儀式のことをいいます。言葉だけでは少し難しく感じるかもしれませんが、イメージとしては「ご遺骨の新しい居場所に落ち着いていただくための大切な時間」と考えると分かりやすいでしょう。
・家族や親しい人が集う大切な時間
納骨の場には、ご家族やご親族、親しい方々が集まります。故人の思い出を語り合い、手を合わせることで、悲しみを共有しながら少しずつ心を落ち着けていくことができます。多くの方が「ようやく区切りを迎えられた」と感じられる、心の支えとなる時間です。
・日本の供養文化における位置づけ
日本の供養文化の中で、納骨は葬儀に続く大切な節目とされています。葬儀で故人を送り出したあと、納骨を行うことで「これからはこのお墓で見守ってください」と祈り、ご先祖様と同じ場所に安らかに眠っていただきます。
・納骨が持つ意味
納骨は、単なる形式的な手続きではありません。残されたご家族にとっては「心の整理」や「故人とのつながりを改めて確かめる時間」となり、故人にとっては「新しい安らぎの場所へ迎え入れられる儀式」となります。
その日を通じて、ご家族が少しずつ前を向くきっかけとなることも多く、「納骨」はまさに故人と家族をつなぐ大切な橋渡しの時間と言えるでしょう。

○納骨の時期について
「四十九日法要」のタイミングが多い
納骨は、故人のご遺骨をお墓に納める大切な儀式です。日本では、四十九日法要と合わせて行うことが一般的です。
四十九日は、故人がこの世を旅立ち仏のもとへと導かれるとされる区切りの日。遺族や親しい方々が集まる法要と一緒に納骨を行うことで、「心の整理」がつきやすく、また親族も参加しやすいというメリットがあります。
一周忌や三回忌に合わせる場合も
ただし、納骨の時期は必ずしも四十九日に限られるわけではありません。さまざまな事情から、一周忌や三回忌の法要と同時に行うケースもあります。
例えば、遠方に住むご親族が集まりやすい日程に調整したり、準備に時間がかかる場合に法要とあわせて行うこともあります。宗派や地域の風習によっても違いがありますので、菩提寺や石材店に相談すると安心です。

「早すぎても遅すぎてもダメ?」という不安について
「納骨は四十九日を過ぎたらもう遅いのでは?」と不安に思われる方もいらっしゃいます。ですが実際には、納骨の時期に明確な決まりはありません。大切なのは、遺族の気持ちや都合にあわせて、無理のないタイミングで行うことです。
あまりに急いで準備を整えないまま当日を迎えるよりも、時間をかけてしっかり準備したほうが安心して臨めるでしょう。
○納骨を依頼する先と手続きの流れ
納骨を行う際は、どの霊園・墓地を利用しているかによって、依頼先や手続きの流れが少し異なります。
ここでは、「民間霊園」「公営霊園」「寺院墓地(寺墓地)」の3つのケースに分けてご紹介します。
・民間霊園の場合
民間霊園で納骨を行う際は、まず霊園の管理事務所へ連絡し、日程の予約を行います。
ご家族の予定や僧侶の都合などを踏まえながら、希望の日時を伝えて調整していく形になります。
また、「納骨式の際にお経をあげてもらいたい」という場合もご安心ください。
多くの民間霊園では、お寺や僧侶と提携しており、霊園を通じて僧侶の手配を依頼することも可能です。
霊園によっては独自の流れがある場合もあるため、事前に管理事務所へ確認しておくとスムーズです。
・公営霊園の場合
自治体が運営する公営霊園では、手続きの流れがやや異なります。
霊園の管理事務所ではなく、指定の石材店に直接連絡して打ち合わせを行うのが一般的です。
石材店との打ち合わせでは、主に次のような内容を決めていきます。
- 納骨の日程調整
- 墓石への戒名彫刻の有無や内容
- 納骨に必要な準備や持ち物の確認
特に公営霊園は利用者が多いため、希望の日程が集中することもあります。早めに相談し、準備を進めておくことが大切です。
・寺院墓地の場合
寺院が管理するお墓の場合は、お寺に直接連絡をして日程を相談します。
住職や寺院担当の方に希望日を伝え、僧侶に読経をお願いする形です。
また、古くからの習慣を重んじるお寺では、服装や供物などの細かな作法が定められている場合もあります。
不安な点や分からないことがあれば、事前に住職や寺院の担当者へ遠慮なく相談するのが良いでしょう。
・石材店ができるサポート
納骨式にあたり、石材店が担う役割はとても幅広く、心強い存在です。
- 納骨作業を行う職人の手配
骨壺を納めるカロート(納骨室)の開閉や石の扱いは専門の職人が対応します。 - 戒名彫刻の打ち合わせ
墓石に戒名や法名、没年月日などを追加で刻む場合、その内容を確認します。 - 僧侶や神職の紹介・当日のサポート
宗派に合わせて僧侶や神職を紹介してくれる場合もあり、当日の進行を支えてくれます。 - お墓の掃除(希望に応じて)
納骨式の前に、墓石や周囲の区画をきれいに整えておくと、当日をより気持ちよく迎えられます。
石材店によっては、お墓の清掃や草取り、花立ての洗浄などを代行してくれる場合もあります。
希望があれば、早めに相談しておくとよいでしょう。
こうしたサポートを活用すれば、ご遺族だけで全てを抱え込まずに済み、落ち着いた気持ちで儀式に臨むことができます。

○納骨に必要な書類
納骨を行うときには、いくつかの書類を確認・準備する必要があります。
「難しそう」と感じるかもしれませんが、基本的には次の2種類がそろっていれば問題ありません。
これらが整っていれば、ほとんどの場合スムーズに納骨を進めることができます。
① 墓地の使用許可証
霊園や寺院から発行される書類で、「この区画のお墓を使用する権利があります」ということを証明するものです。
納骨時にはこの書類の提示が必須で、これがないと遺骨を納めることができません。
「使用許可証」は、お墓を契約した際に霊園や寺院から必ず発行されます。
書類のサイズはA4またはB5ほどが多く、霊園名・区画番号・使用者の氏名などが記載されています。
普段は紛失しないよう、契約書類と一緒に保管しておくと安心です。
② 埋葬(火葬)許可証 または 改葬許可証
- 埋葬(火葬)許可証
市区町村の役所から交付される書類で、「このご遺骨は火葬が完了しており、納骨しても問題ありません」ということを証明するものです。
葬儀を行った際に、葬儀社を通して火葬場で受け取るのが一般的です。
納骨時には、必ず原本を持参して霊園に提示します。 - 改葬許可証
すでに別のお墓に納められているご遺骨を、新しいお墓へ移す(改葬する)場合には、「改葬許可証」が必要になります。
これは、現在遺骨がある市区町村の役所に申請して発行してもらう書類です。
新しい墓地で納骨を行う際、この書類がないと受け入れてもらえないため、改葬手続きの際は特に注意が必要です。
紛失してしまった場合(使用許可証)
「墓地の使用許可証をなくしてしまった」という場合でも、慌てる必要はありません。
契約した霊園や寺院に連絡をすれば、再発行の手続きをしてもらえます。
再発行時には、契約者本人であることを確認するため、
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
の提示を求められる場合があります。
また、霊園によっては、
- 再発行の手数料がかかる
- 住民票や戸籍謄本などの補助書類が必要になる
といったケースもあります。
どのような手続きが必要かは、まず霊園や寺院の管理事務所に問い合わせて確認すると安心です
○納骨式の準備と持ち物
納骨式は、故人を偲び、心を込めてお見送りする大切な時間です。事前に必要なものを準備しておくことで、当日を落ち着いた気持ちで迎えることができます。ここでは代表的な持ち物と注意点をご紹介します。
・お花
納骨式では、お墓に花を供えるのが一般的です。
- 白い菊やユリなどの落ち着いた花
- 季節のお花(春は桜やチューリップ、夏はひまわりなど)
- 故人が好きだった花
色合いは、派手すぎず落ち着いたものを選ぶのが基本です。
ただし、最近では「明るい色で華やかに送ってあげたい」と希望されるご家族も増えています。
ご家族の意向や宗派の習慣にあわせて選ぶとよいでしょう。

・お供物
故人が生前に好んでいた食べ物や飲み物をお供えすると、参列者の心が温まり、思い出話にもつながります。
- 果物やお菓子
- 故人の好きだった飲み物(お茶・コーヒーなど)
- お線香やろうそく
ただし、食べ物や飲み物のお供えを長時間置きっぱなしにすると、腐敗やカラス・虫による被害につながることがあるため、最後には必ず持ち帰るようにしましょう。
・故人のお写真・位牌
納骨式の際に、故人のお写真を持参するのもおすすめです。
お墓の前に写真を飾って手を合わせることで、故人の存在をより身近に感じながらお参りすることができます。
また、位牌の開眼供養(魂入れ)を行う場合は、
・お葬式のときに用いた「白木の位牌」
・新たに作った「本位牌」
の両方を持参し、僧侶にご供養をお願いしましょう。
開眼供養とは、位牌に「故人の魂をお迎えする儀式」であり、納骨式と同時に行う方も多くいらっしゃいます。
・当日の服装マナー
納骨式は法要の一つにあたるため、服装も「落ち着き」と「清潔感」が大切です。
- 喪主やご家族は黒い喪服を着用
- 参列者は略式の喪服、もしくは落ち着いた色のスーツやワンピースでも可
真っ赤や鮮やかな色など、派手な服装は控えるのが望ましいです。「法要にふさわしい落ち着いた服装」という意識を持つと安心です。
季節によっては、暑さ・寒さ対策も大切です。
夏は薄手でも黒を基調とした服装、冬は黒いコートを羽織るなどして、清楚な印象を心がけましょう。
納骨式の準備は、故人に心を込めて向き合う時間でもあります。形式にとらわれすぎず、「故人が喜んでくれるかどうか」を基準に準備することが一番大切です。
○おわりに
納骨は、故人を偲び、ご家族が心を込めてお見送りする大切な儀式です。書類の準備や日程の調整など、やることが多く不安に感じる方も少なくありませんが、事前に流れを知っておくことで安心して当日を迎えることができます。
大切なのは「形を整えること」以上に、「故人に喜んでもらえるかどうか」という気持ちです。きれいなお花を供えたり、好きだった食べ物をお供えしたりと、想いを込めて準備することで、納骨式は温かく心に残る時間になります。
分からないことがあれば、霊園の管理事務所や石材店に相談してください。経験豊富なスタッフがサポートしてくれるので、不安を一人で抱え込む必要はありません。
納骨を通してご家族の気持ちが少しずつ落ち着き、故人との絆を改めて感じられる──そのお手伝いができれば幸いです。
監修者情報

渡辺裕
(わたなべゆたか)
1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。実家が石材店のため、小さい頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。
有限会社 千代田家石材店/代表取締役
一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00
一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級
一般社団法人 日本看取り士会/看取り士
一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士
ーお墓に関するご相談ならぜひ千代田家石材店にー
当社は大正8年に八柱霊園の参道に創業してから100余年。
千代田家石材店は、お客様に寄り添ったご提案・ご法要・お墓参りのお手伝いをさせて頂いています。
埼玉県さいたま市の岩槻北稜霊園のほか、埼玉、茨城、千葉県内に多数お取り扱いの霊園がございます。
ご埋葬やお墓の購入、お墓のリフォームなど、お墓やご法要に関することでしたら、何でもご相談ください!
有限会社 千代田家石材店
住所:〒270-2253 千葉県松戸市7-450(八柱霊園 中参道)
営業時間:8:00〜19:00(土日祝日営業)
店舗定休日:火曜(祝日・お盆・お彼岸・年末年始を除く)
※各霊園のご案内は随時行っております。
TEL/FAX:047-387-2929/047-389-0088
HP:https://chiyodaya.co.jp/
ーその他の霊園ー
【2023年11月23日 新区画オープン】