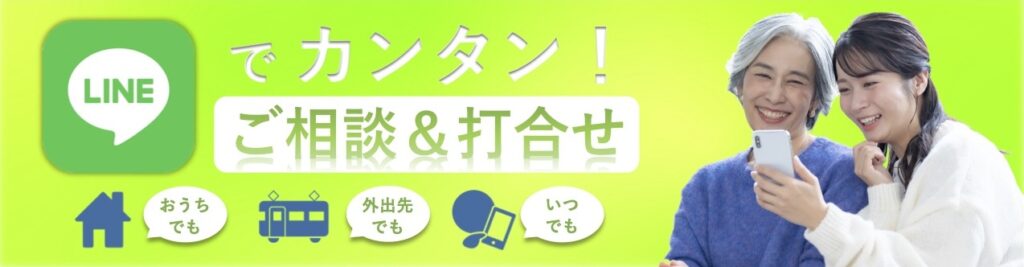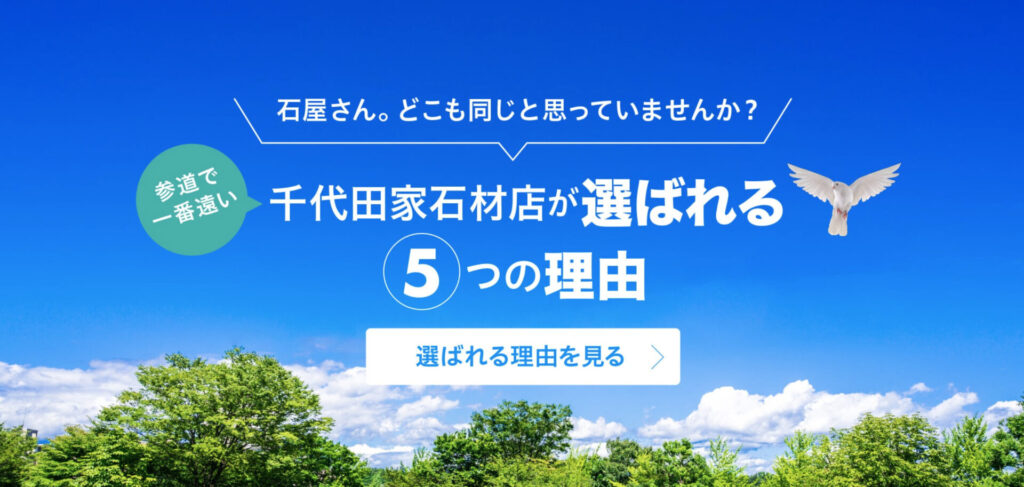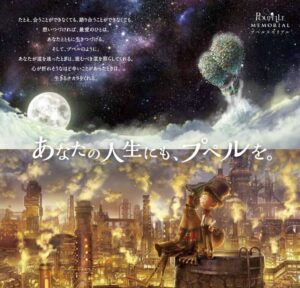お彼岸の由来と意味を知ろう|供養と心を整える時間の大切さ

「お彼岸」と聞くと、多くの方は「お墓参り」や「おはぎ」を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、本来のお彼岸は、ただ先祖を偲ぶ行事ではなく、仏教の教えや日本独自の自然信仰が結びついた深い意味を持つ期間です。
なぜ春分と秋分の日を中心に行われるのか?「彼岸」という言葉にはどのような由来があるのか?この記事では、お彼岸の意味と起源に焦点を当ててわかりやすく解説していきます。
「お彼岸とは何かを正しく知りたい」「他の記事より深い背景を理解したい」という方に向けて、伝統と現代をつなぐ視点でお届けします。
●お彼岸とは何か?基本から学ぶ
お彼岸とは、日本における伝統的な行事であり、春分の日・秋分の日を中心に前後3日を含む7日間を指します。この期間を「彼岸」と呼び、ちょうど昼と夜の長さがほぼ等しくなる特別な時期です。
天文学的に見ても、春分と秋分は「太陽が真東から昇り、真西に沈む日」。仏教では西の方角が極楽浄土のある方向とされることから、この期間は「現世と来世の距離が最も近づく」と信じられてきました。
そのため、お彼岸は単なる季節の行事ではなく、自然のリズムと仏教思想が重なり合う象徴的な時間なのです。
・「彼岸」という言葉の由来と仏教思想
お彼岸の「彼岸(ひがん)」は、じつは仏教のキーワードです。反対の言葉は「此岸(しがん)」で、こちらは“いま私たちが生きている世界”。迷いや不安、怒りや欲ばり心――そうした煩悩(ぼんのう)が渦まく側を「此岸」と呼びます。
それに対して、「彼岸」は悟りの境地、心が静かでゆらがない状態のこと。お彼岸は、此岸から彼岸へ「渡る」ために心を整える期間だと理解すると、ぐっと本質がつかみやすくなります。
・ことばの由来はサンスクリット語「波羅蜜多(パーラミータ)」
「彼岸へ渡る」ことを支える実践を、仏教では波羅蜜(はらみつ/はらみった)、あるいは波羅蜜多(はらみった・パーラミター)と呼びます。
サンスクリット語の pāramitā は直訳すると「完全・完成」「向こう岸に到ること」という意味。つまり「波羅蜜」は、迷いの岸(此岸)から悟りの岸(彼岸)へ渡るための“渡し舟”のような実践を指します。
・「此岸」と「彼岸」のちがい
- 此岸(しがん)
思い通りにならない現実に心が振り回される世界。焦り・比較・怒り・不安などに引っぱられがち。 - 彼岸(ひがん)
ものごとをありのままに見て、執着に縛られない心の状態。落ち着き・やさしさ・感謝が自然にあらわれる。
お彼岸は、自然(春分・秋分)という節目に合わせて、「心のモードを切り替える」期間でもあります。太陽が真西に沈むこの時期、西方にあると説かれる極楽(理想の心のあり方)を思い、自分の心を“西”へと向け直すわけです。
・六波羅蜜(ろくはらみつ)|彼岸へ渡る6つの実践
悟りへの渡し舟=波羅蜜の代表が六波羅蜜です。むずかしく感じる言葉ですが、日常に置き換えると“心を整える6つの習慣”。一つずつ、やさしく説明します。
- 布施(ふせ)
布施とは、お金や物を与えることだけに限りません。
特別なことではなく、日常の中で自然にできる小さな思いやりのこと。道で「お先にどうぞ」と声をかけたり、ちょっとした「ありがとう」を伝えるだけでも、立派な布施になるのです。 - 持戒(じかい)
ルールを守る・約束を守る・正直にふるまう、という日々の倫理。
たとえば「時間を守る」「嘘をつかない」「交通ルールを守る」。
人に迷惑をかけないという姿勢全体が“持戒”です。 - 忍辱(にんにく)
イヤな出来事や言葉に出会っても、一度深呼吸して受け止めること。
反射的に言い返したりカッとなるのではなく、感情に飲み込まれない練習です。
「いま自分は怒っているな」と気づけたら、それがもう一歩前進。 - 精進(しょうじん)
いきなり完璧を求めず、コツコツ続ける力。
5分の片づけ、10分の散歩、1ページの読書でもOK。“毎日少しずつ”が最大の近道です。 - 禅定(ぜんじょう)
心を静め、いまこの瞬間に注意を戻すこと。
1分間の深呼吸、スマホを置いてお茶を味わう、歩くときに足裏の感覚に意識を向ける――これも立派な禅定です。 - 智慧(ちえ)
単なる知識ではなく、ものごとを偏見なく見る力。
「自分の思い込みは何だろう?」と問い直す習慣が、智慧を育てます。
事実と解釈を分けて考える――それだけで心は軽くなります。
🔍 ポイント
六波羅蜜は“修行のカタログ”ではありません。完璧にやる日が1日もなくても、向きを変え続けること自体が「渡る」こと。お彼岸は、その方向転換をやさしく後押ししてくれる季節です。
・「語源の知識」で終わらせない――“渡る”とは生き方の比喩
「波羅蜜多=彼岸へ到る」と聞くと遠い世界の話に思えますが、日々の小さな選択がそのまま“渡る”ことにつながります。
- 今日は誰かに一言、やさしい言葉をかける(布施)
- 約束の時間をきちんと守る(持戒)
- 不快な言葉に即反応せず、いったん黙って水を飲む(忍辱)
- できる範囲で積み重ねる(精進)
- 1分だけ呼吸に意識を向ける(禅定)
- 思い込みを手放して相手の立場も想像する(智慧)
こうした暮らしの姿勢”の総和が、此岸から彼岸へと心を運ぶ。お彼岸は、その方向に舵(かじ)を切り直す一年の節目、と言えるでしょう。

●お彼岸が日本に根付いた歴史的背景
お彼岸という行事は、単に「仏教から伝わったもの」ではありません。
日本に古くからあった祖先を敬う信仰や自然を大切にする感覚が、仏教の思想と重なり合うことで独自に形づくられました。その融合こそが、お彼岸を日本人の暮らしに深く根づかせた大きな理由です。
・日本古来の祖先信仰と結びつき
日本では、仏教が伝わる以前から祖霊信仰(それいしんこう)と呼ばれる風習がありました。これは「亡くなった先祖の霊は、今を生きる家族を見守ってくれている」という考え方です。お盆や正月と同じく、お彼岸もこの祖霊信仰と強くつながっています。
仏教が「彼岸=悟りの境地」という教えを説いたとき、日本人はそれを「先祖の魂が安らかに暮らす世界」として理解しました。つまり、仏教の彼岸思想と日本古来の祖先供養の心が自然に融合したのです。
・春分・秋分と自然信仰、農耕文化の節目
お彼岸が春分と秋分にあたるのも偶然ではありません。
- 春分は「農作業の始まり」
- 秋分は「収穫を感謝する時期」
この二つは古来より日本の農耕文化において命の循環を感じる節目でした。
昼と夜の長さがほぼ同じになる特別な日が、自然への畏敬と感謝を表す日として位置づけられ、そこに仏教の「彼岸」の考え方が結びついたのです。
さらに「太陽が真西に沈む」ことも重要でした。西の方角には極楽浄土があるとされるため、この日を境に“あの世とこの世がつながりやすい時期”と考えられたのです。
・平安時代以降の定着と広がり
お彼岸がはっきりと行事として定着したのは平安時代と言われています。
当時、天皇家や貴族の間で仏教行事が盛んになり、その中でお彼岸の法要も行われるようになりました。やがて武士や庶民の間にも広がり、先祖供養をする時期として社会全体に根づいていったのです。
江戸時代に入ると、寺請制度(檀家制度)によってお寺と人々の関わりがさらに深まり、お彼岸は「家ごとの先祖供養」として定番化。春と秋、年に2回の大切な行事として今日まで続いてきました。
●お彼岸の本質的な意味
お彼岸というと「お墓参り」や「先祖供養」のイメージが強いですが、本質はもっと深いところにあります。日本人は古来より、この時期を「あの世とこの世がつながる特別な期間」と考えてきました。そして、その考えは単に亡き人を偲ぶだけではなく、生きている私たち自身の心を整える時間へとつながっていきます。
・あの世とこの世の境界が近づく期間
春分・秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈む日。仏教では西に極楽浄土があるとされているため、この世(此岸)とあの世(彼岸)が最も近づくときと信じられてきました。
この考え方から、「先祖や故人の魂が私たちのそばに帰ってくる」「生きている私たちも彼岸を想うことで心が清められる」と受け止められるようになったのです。
つまりお彼岸は、亡き人とつながり直す時間であり、生きている自分を見つめ直す節目でもあるのです。
・供養だけでなく「心を整える」時間
お彼岸の本質は、単にお墓参りをすることにとどまりません。
もともと仏教では、お彼岸は 「自分自身の心を整え、煩悩にとらわれない生き方を目指す期間」 とされていました。
忙しい日常の中で、つい人と比べたり、欲に振り回されたりしてしまうのは誰にでもあること。お彼岸はそうした生活をリセットして、「どう生きるか」「どんな心で人と関わるか」を考え直すための時間でもあるのです。
・六波羅蜜の実践=日常生活の見直し
第2章で紹介した「六波羅蜜(ろくはらみつ)」は、彼岸へ渡るための6つの実践でした。
これを日常にあてはめると、お彼岸は単なる宗教行事ではなく、暮らし方や心の習慣を見直すチャンスになります。
- 布施(ふせ)ちょっとした思いやりや親切を心がける
- 持戒(じかい)約束やルールを守る
- 忍辱(にんにく)嫌なことがあってもすぐ反応せず、落ち着く
- 精進(しょうじん)小さな努力を毎日続ける
- 禅定(ぜんじょう)深呼吸や瞑想で心を静める
- 智慧(ちえ)ものごとを偏りなく見る習慣を持つ
これらを意識することは、亡き人のためだけでなく、自分自身をより良い方向に導く“心の修行”とも言えます。
●現代における「意味」と再発見
お彼岸というと「昔からある伝統行事」と思われがちですが、実は現代社会にこそ必要とされる意味を持っています。忙しい日常の中で立ち止まり、心を見直す節目としての価値や、家族や社会とのつながりを深めるきっかけとして、いま改めて注目するべき行事なのです。
・忙しい現代に「心の節目」を与える
現代人は、仕事や学業、スマートフォンやSNSに追われ、心が休まる時間を見失いがちです。そんな中でお彼岸は、季節の変わり目に「一度立ち止まって心を整える」機会を与えてくれます。
たとえば、お墓参りに行くこと自体が「ゆっくり自然に触れる時間」となり、普段は忘れがちな家族への感謝や、亡き人への思いを思い出させてくれるでしょう。お彼岸は、現代社会における“心のリセットボタン”とも言える存在なのです。
・家族や親戚が集まるきっかけとしての社会的な意味
核家族化や地域社会のつながりの希薄化が進む中、お彼岸は家族や親戚が顔を合わせる数少ない機会でもあります。
- お墓参りの後に家族で食事をする
- 親戚同士で近況を報告し合う
- 子どもに「先祖を大切にする気持ち」を伝える
こうした時間は、単に先祖を供養するだけでなく、生きている家族同士の絆を再確認する場となります。お彼岸は、世代を超えて心をつなぐ「社会的な役割」を担っているのです。
・テクノロジー時代に広がる「新しいお彼岸」
近年はライフスタイルの変化や移動の制約もあり、お彼岸の形も進化しています。
- オンライン供養
インターネットを通じて僧侶に読経を依頼する - 代理参りサービス
遠方に住む家族の代わりにお墓参りを代行 - ビデオ通話での参加
親戚が集まる場にリモートで参加
これらは「伝統を守りながらも時代に合わせて柔軟に形を変えていく」お彼岸の新しい姿です。テクノロジーを取り入れることで、距離や時間にとらわれず先祖を敬う心をつなぐことが可能になりました。
●おわりに
お彼岸は、先祖を想う大切な行事であると同時に、私たち自身の心を見つめ直す時間でもあります。忙しい毎日の中で、立ち止まるきっかけを与えてくれるこの期間は、まさに心の休憩時間といえるでしょう。
「最近少し慌ただしいな…」と感じている方も、お彼岸にはほんの少し立ち止まってみてください。お墓参りに足を運ぶのも良し、心の中でご先祖様に手を合わせるのも良し。やり方は人それぞれですが、感謝の気持ちを持つこと自体が一番の供養になります。
そして、先祖を偲ぶ時間は、同時に「今をどう生きるか」を考える時間でもあります。お彼岸を通じて、家族のつながりや自分の心を大切にする気持ちを、ぜひもう一度思い出していただければと思います。
今年のお彼岸が、みなさまにとって 心を整え、あたたかい気持ちになれる時間となりますように。
監修者情報

渡辺裕
(わたなべゆたか)
1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。実家が石材店のため、小さい頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。
有限会社 千代田家石材店/代表取締役
一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00
一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級
一般社団法人 日本看取り士会/看取り士
一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士
ーお墓に関するご相談ならぜひ千代田家石材店にー
当社は大正8年に八柱霊園の参道に創業してから100余年。
千代田家石材店は、お客様に寄り添ったご提案・ご法要・お墓参りのお手伝いをさせて頂いています。
埼玉県さいたま市の岩槻北稜霊園のほか、埼玉、茨城、千葉県内に多数お取り扱いの霊園がございます。
ご埋葬やお墓の購入、お墓のリフォームなど、お墓やご法要に関することでしたら、何でもご相談ください!
有限会社 千代田家石材店
住所:〒270-2253 千葉県松戸市7-450(八柱霊園 中参道)
営業時間:8:00〜19:00(土日祝日営業)
店舗定休日:火曜(祝日・お盆・お彼岸・年末年始を除く)
※各霊園のご案内は随時行っております。
TEL/FAX:047-387-2929/047-389-0088
HP:https://chiyodaya.co.jp/
ーその他の霊園ー
【2023年11月23日 新区画オープン】