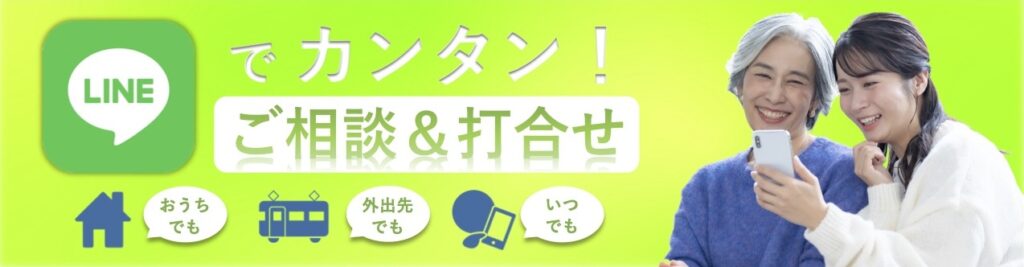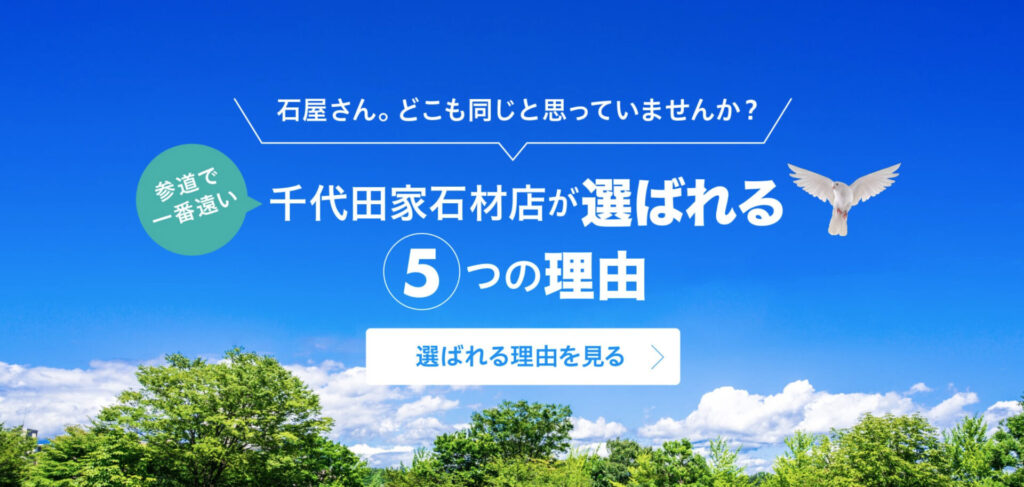塔婆とは?意味・費用・お墓に立てる意味や時期まで初心者にもわかりやすく説明します
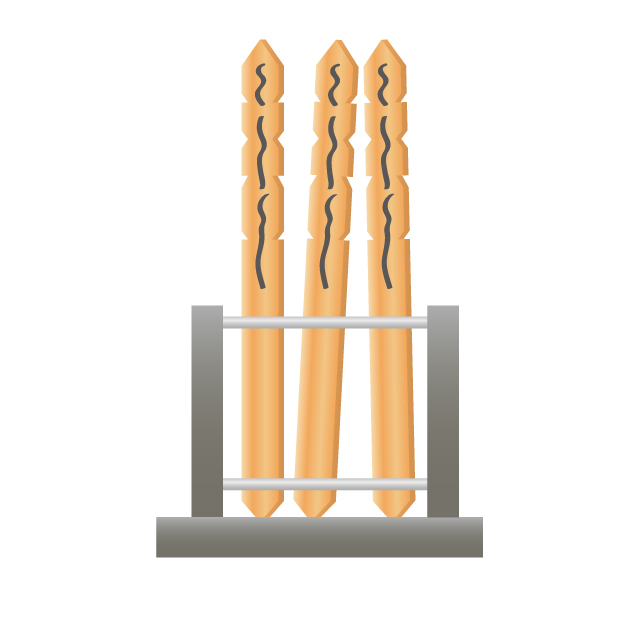
「お墓参りのときに、木の板のようなものが立っているのを見たことがある」
そんな経験はありませんか?
あれは「塔婆(とうば)」と呼ばれるもので、仏教において大切な意味を持つ供養の一つです。見た目はとてもシンプルですが、実は故人やご先祖様への深い想いが込められています。
「塔婆ってなんのために立てるの?」
「どれくらいの金額がかかるの?」
「いつまで立てておけばいいの?」
そんな素朴な疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「塔婆とは何か」という基本から、立てる意味・費用の相場・書かれている内容・いつ立てるのか・いつまで置いておくのかなど、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
ご自身やご家族の供養の際に、安心して塔婆供養ができるように──
大切なひとときを、心からの祈りの時間にできるように──
ぜひ最後までお読みください。
目次
○お塔婆ってなに?
お墓の後ろや横に、細長い木の板が立っているのを見たことはありませんか?
それが「塔婆(とうば)」と呼ばれるものです。
一見すると、ただの板のように見えるかもしれませんが、実はとても大切な仏教の供養の道具です。
▼仏教における「供養」のひとつ
塔婆は、亡くなった方の冥福(めいふく)を祈るために立てるもので、
仏教では、故人のために善い行い(=供養)をすることが大切だとされています。
塔婆を立てることもそのひとつで、心を込めた供養のあらわれと考えられています。
▼卒塔婆(そとば)ってなに?語源はインドに
「塔婆」は正式には「卒塔婆(そとば)」といい、
その言葉の由来は、古代インドの「ストゥーパ」という仏塔(お墓や供養のための塔)にあります。
もともとストゥーパは、お釈迦さまや高僧の遺骨を納めるために建てられた仏塔でした。
それを日本では木の板のかたちに簡略化し、供養の象徴として立てるようになったのです。

○塔婆はなぜ立てるの?|供養の意味と目的
塔婆を立てるのは、亡くなった方への供養としての意味があります。
私たちが手を合わせ、塔婆を立てることで、故人の冥福(めいふく)を祈る──それが塔婆供養の本来の目的です。
▼故人やご先祖様への「追善供養(ついぜんくよう)」
塔婆は、亡くなった方のために「善い行い(=善行・功徳)」を積むために立てられます。
仏教では、生きている人が行う善行は、亡き人にも届くとされています。
そのため、法要の際やお盆・お彼岸などの節目に、塔婆を立てて祈りを捧げることで、
「あなたのことを忘れていません」「安らかに過ごせますように」
という願いを届けているのです。
▼無縁仏への祈りも込めて
塔婆供養は、ご家族やご先祖様だけでなく、縁のない仏さま(無縁仏)への祈りとしても行われることがあります。
行き場のない魂を想い、心を寄せることも、大切な供養のかたちのひとつです。
塔婆を立てるという行為は、
亡き人を想い、今を生きる私たちができるやさしい祈りのかたち。
「何のために立てるの?」と疑問に思っていた方も、
その背景を知ることで、きっと手を合わせる気持ちが深まるのではないでしょうか。
○どんなときに塔婆を立てるの?
「塔婆はいつ立てるものなの?」
そう思われる方も多いかもしれません。塔婆を立てるタイミングにはいくつかありますが、一般的には故人を偲ぶ節目の法要や、季節の供養の時期に行われることが多いです。
以下に代表的な時期を詳しくご紹介します。
▼四十九日法要
亡くなってから49日目に行う法要です。仏教では、人は亡くなってから49日間のあいだに来世の行き先が決まるとされ、この期間を「中陰(ちゅういん)」と呼びます。
そのため、四十九日の法要はとても重要な節目とされ、塔婆を立てて故人の旅立ちを見守り、安らかな成仏を祈ります。
▼ 一周忌・三回忌などの年忌法要
一周忌(亡くなってから1年目)や三回忌(2年目)をはじめとする年忌法要でも、塔婆を立てて供養を行います。
年忌法要は、故人の命日を迎えるにあたり、その方の生前のことを思い出しながら冥福を祈る大切な行事です。
塔婆を通して「今も忘れていません」「これからも見守ってくださいね」という気持ちを届ける役割も担っています。
▼お盆やお彼岸などの季節の供養
毎年訪れるお盆(7月または8月)や、春・秋のお彼岸の時期には、
ご先祖様が帰ってくると信じられており、多くの方が墓前に手を合わせます。
この時期にも、ご先祖様のために塔婆を立てる方が多くいらっしゃいます。
とくにお寺でお盆法要や彼岸法要が行われる際には、まとめて塔婆を申し込む機会も多く、霊園や寺院によっては毎年定例のように案内されることもあります。
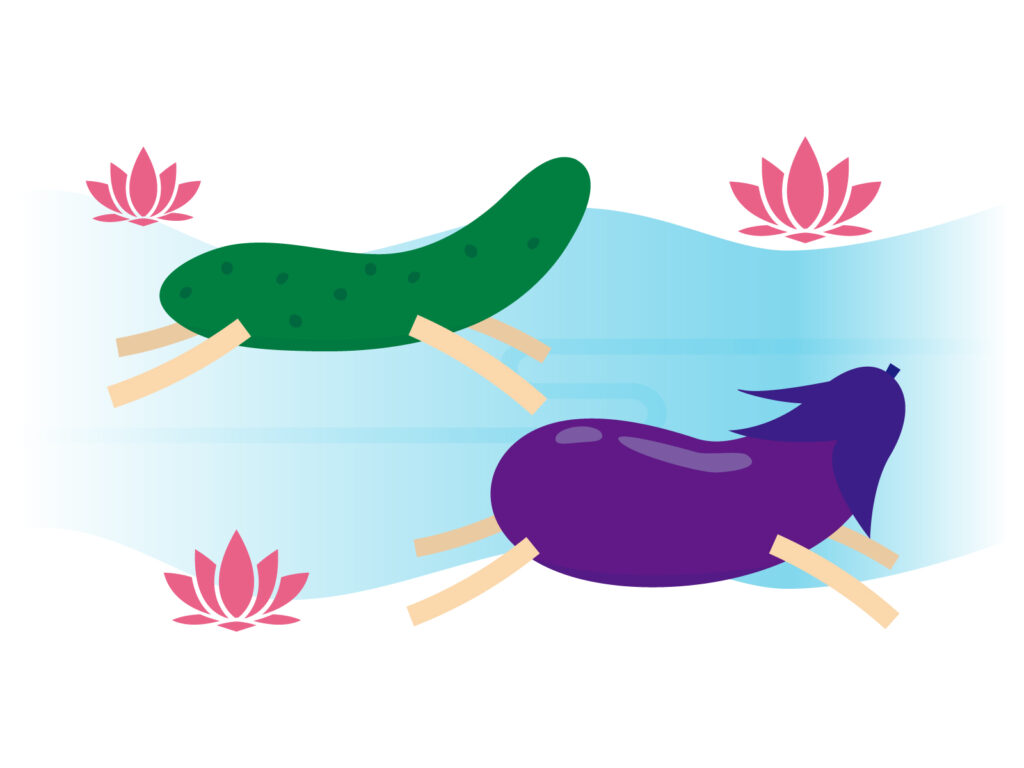
▼その他の特別な祈りを込めたいときにも
法要や季節の行事以外にも、
- 故人の誕生日や命日
- 新たなご供養を始めたいとき
- 気持ちの節目として何か供養をしたいとき
など、ご家族が「供養したい」と感じたときに塔婆を立てることもあります。
決まりごとにとらわれず、心のままに祈ることもまた、供養の大切なかたちのひとつです。
塔婆を立てるタイミングに迷ったときは、お寺や霊園に相談すれば、
そのときの状況やご家族の思いに合った方法を案内してもらえます。
大切なのは、形よりも、「故人を思う心」であることを、どうぞ忘れずにいてくださいね。
○塔婆の費用ってどれくらい?
「塔婆をお願いしたいけれど、費用はどのくらいかかるの?」
初めての方にとっては、気になるポイントですよね。
一般的に、塔婆の費用は1本あたり3,000円〜5,000円程度が多いとされています。
ただし、これはあくまで目安で、実際の金額は塔婆の長さや形、地域やお寺の方針によって異なります。
もし不安なときは、お寺や霊園の担当者に確認してみましょう。
多くの場合、費用はあらかじめ定められているので、「いくらくらいですか?」とお聞きいただいてまったく問題ありません。
「金額のことを聞くのはちょっと失礼かも…」と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、大丈夫です。皆さん同じように疑問をお持ちなので、ご安心くださいね。
○塔婆はいつまで立てておけばいいの?|撤去のタイミング
「塔婆って、一度立てたらずっと置いておくものなの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いと思います。
実は、塔婆をいつまで立てておくかには、明確な決まりはありません。
けれども、現場ではいくつかの一般的な目安があり、それに沿って対応されることが多いです。
▼ 年忌法要ごとに新しい塔婆に立て替える
もっともよくあるのは、年忌法要(1周忌、3回忌など)のたびに新しい塔婆を立て、古いものは撤去するという方法です。
節目ごとに新たな塔婆を立てることで、その都度改めて供養の気持ちを込めることができます。
▼古くなった塔婆は「お焚き上げ」されることが多い
塔婆は仏具のひとつであるため、粗末に扱うことは避けなければなりません。
そのため、古くなった塔婆は、お寺で「お焚き上げ(おたきあげ)」と呼ばれる儀式の中で、丁寧に焼却供養されることが一般的です。
塔婆に限らず、仏具やお札なども同じように、感謝と敬意を込めて処分されるのが仏教の考え方です。
▼無理に残しておく必要はありません
「せっかく立てたから、できるだけ長く置いておきたい」と思われる方もいらっしゃいます。
もちろん、そのお気持ちも大切にしていただいて問題ありません。
ただし、風雨にさらされて劣化してしまった塔婆をそのままにしておくと、かえって見た目が気になることもありますし、管理上の問題になることも。
供養の心は、塔婆の“期間”よりも、立てるときの“思い”が大切です。
いつかは撤去することを前提に、必要に応じて新しい塔婆へと切り替えていきましょう。
塔婆の取り扱いに迷ったときは、お寺や霊園の担当者に相談してみてください。
きっと丁寧に教えてくれるはずです。
塔婆は「祈りのかたち」。
その役目を終えたあとは、感謝の気持ちで送り出してあげましょう。
○塔婆は誰がお願いするの?|手配の仕方と注意点
塔婆を立てたいと思ったとき、
「どこに、誰にお願いすればいいの?」と迷われる方も多いのではないでしょうか。
塔婆は、ご家族やご親族が故人やご先祖様の供養のために手配するものです。
手続きはそれほど難しくありませんが、いくつかの注意点がありますので、順を追ってご説明します。
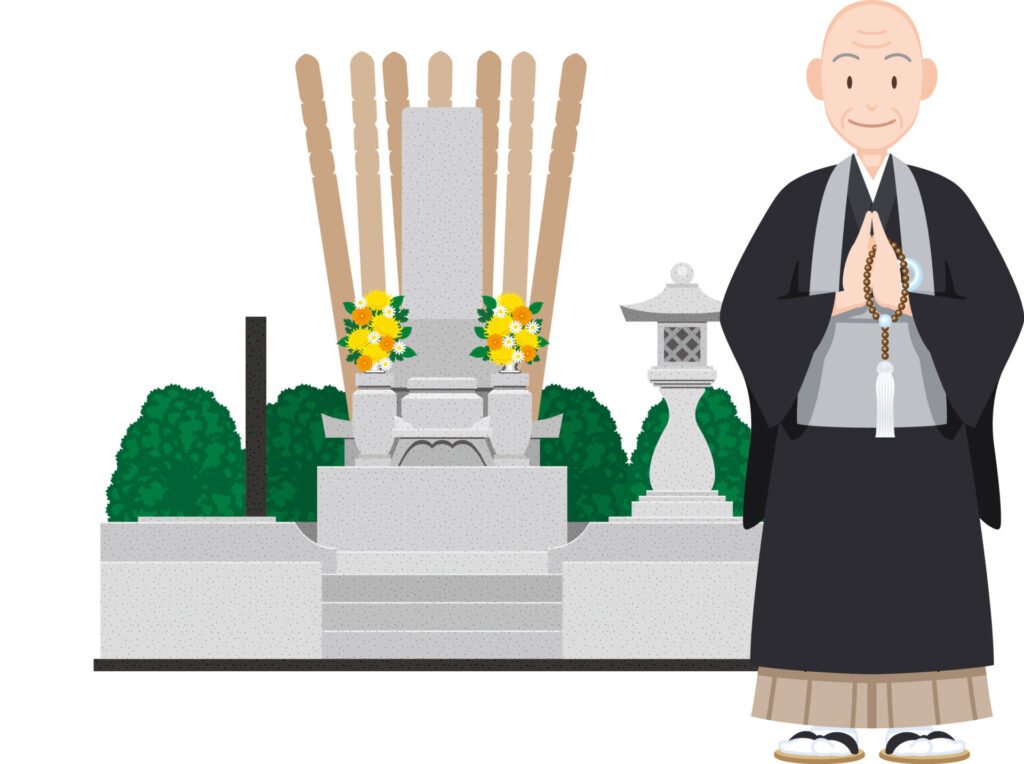
▼法要を行う場合は、まずお寺に相談を
四十九日や一周忌など、法要をお寺で行う場合には、基本的にそのお寺へ直接依頼をします。
塔婆の準備には、故人の戒名や命日などの情報が必要ですので、早めに連絡して申し込むのが安心です。
法要当日までに間に合うよう、できれば1~2週間前には相談しておくとよいでしょう。
また、お寺によっては塔婆の種類や本数に決まりがあることもありますので、わからないことがあれば遠慮なく確認しましょう。
▼霊園の場合は管理事務所へ
民間霊園などでは、霊園の管理事務所で塔婆の申し込みを受け付けている場合があります。
申込書の記入や、管理費と合わせたお支払いなど、各霊園のルールに従って手配します。
お盆・お彼岸など、塔婆の申し込みが集中する時期には申し込み期限が決まっている場合も多いため、早めの確認がおすすめです。
▼ 日程には余裕を持って申し込みを
塔婆は、申し込んでからすぐに立てられるものではありません。
手書きで戒名や梵字を書く場合もあり、準備にはある程度の時間がかかります。
特にお盆・彼岸・法要シーズンなどは申し込みが集中しますので、できるだけ早めに申し込むのがベストです。
「1週間前までに申し込んでください」といった期限を設けているお寺や霊園も多いため、早めの行動を心がけましょう。
○塔婆がなくても大丈夫?
法事を控えて、「塔婆がないとダメ?」と心配されている方もいらっしゃるでしょう。結論から申し上げますと、お塔婆は丁寧な供養の一つではありますが、必ずしも立てなければならないものではありません。
以下では、お塔婆の意味や宗派ごとの違いを踏まえ、「塔婆がなくても問題ない」理由について丁寧にご説明します。大切なのは形ではなく、故人を想うお気持ちです。ですから、どうぞ安心して法事の準備を進めてください。
▼塔婆は必ずしも必要ではありません
お塔婆は丁寧な供養の形ではありますが、必ず立てなければならない決まりではありません。地域や寺院の風習、宗派の教えによっては塔婆供養自体を行わない場合もあります。
実際、「必ず塔婆を立てないと供養ができない」ということはなく、塔婆を立てなくても故人を供養することは十分可能です。お塔婆を立てないことがマナー違反ではないかと不安に感じる必要はありません。それよりも大切なのは、故人を思いやるお気持ちをもって法事に臨むことです。
▼宗派による違い|浄土真宗では塔婆供養を行わない
仏教の宗派によって、お塔婆に対する考え方には違いがあります。
たとえば浄土真宗では、基本的にお塔婆を用いた供養を行いません。浄土真宗の教えでは、故人は亡くなった後ただちに阿弥陀如来の救いによって極楽浄土へ往生できると考えられており、塔婆を立てて冥福を祈る追善供養の必要がないからです。
このように宗派の教義によっては、初めから塔婆供養という習慣がない場合もあります。一方、浄土真宗以外の多くの宗派(浄土宗・真言宗・曹洞宗など)では法事の際に塔婆供養を行うのが一般的です。しかし、それでも塔婆を立てるかどうかは各ご家庭の判断や寺院の方針に任されていることが多いです。なお、同じ宗派であっても地域や寺院の慣習によって対応が異なる場合があります。そのため、「うちの宗派ではどうすべきかしら?」と心配な時は、菩提寺(お付き合いのあるお寺)に相談してみるとよいでしょう。
▼故人を想う気持ちが何より大切
形式よりも大切なのは、故人を偲び、想う心です。どのような供養の形をとるにせよ、故人への感謝や愛情を込めてお祈りするお気持ちが一番の供養になります。お塔婆はあれば丁寧な供養にはなりますが、無くても故人を思うお気持ちさえあれば問題ありません。
実際、葬儀や法要といった儀式は亡くなった方のためというより、今を生きる遺族が故人を偲んで心の区切りをつけるためのものだともいわれています。大事なのは、ご家族が故人との思い出を振り返り、感謝の気持ちを持って心安らかに法事の時間を過ごすことです。
お塔婆を用意しない場合でも、たとえば法事の際にお線香やお花を手向けたり、心を込めてお経を唱えることで充分に供養の気持ちは伝わります。形式にとらわれすぎず、「故人を大切に思う心」をもって供養して差し上げてください。それが何よりの供養となるはずです。

○おわりに
塔婆とは何か、なぜ立てるのか、いつ・どのように立てるのか…。
初めての法要を迎える方にとっては、わからないことばかりかもしれません。
でもご安心ください。塔婆はあくまで供養のひとつの形であり、大切なのは「故人を想う心」です。宗派や霊園のルールに応じて柔軟に対応しながら、ご家族の思いに合った方法で供養を行っていただければ、それが何よりの供養となります。
迷ったときは、お寺や霊園に相談しながら、安心して一歩ずつ準備を進めていきましょう。供養の時間が、やさしく温かいものとなりますように。
監修者情報

渡辺裕
(わたなべゆたか)
1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。実家が石材店のため、小さい頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。
有限会社 千代田家石材店/代表取締役
一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00
一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級
一般社団法人 日本看取り士会/看取り士
一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士
ーお墓に関するご相談ならぜひ千代田家石材店にー
当社は大正8年に八柱霊園の参道に創業してから100余年。
千代田家石材店は、お客様に寄り添ったご提案・ご法要・お墓参りのお手伝いをさせて頂いています。
埼玉県さいたま市の岩槻北稜霊園のほか、埼玉、茨城、千葉県内に多数お取り扱いの霊園がございます。
ご埋葬やお墓の購入、お墓のリフォームなど、お墓やご法要に関することでしたら、何でもご相談ください!
有限会社 千代田家石材店
住所:〒270-2253 千葉県松戸市7-450(八柱霊園 中参道)
営業時間:8:00〜19:00(土日祝日営業)
店舗定休日:火曜(祝日・お盆・お彼岸・年末年始を除く)
※各霊園のご案内は随時行っております。
TEL/FAX:047-387-2929/047-389-0088
HP:https://chiyodaya.co.jp/
ーその他の霊園ー
【2023年11月23日 新区画オープン】