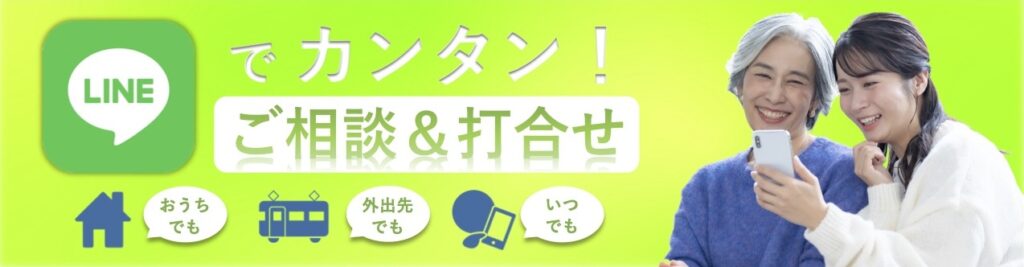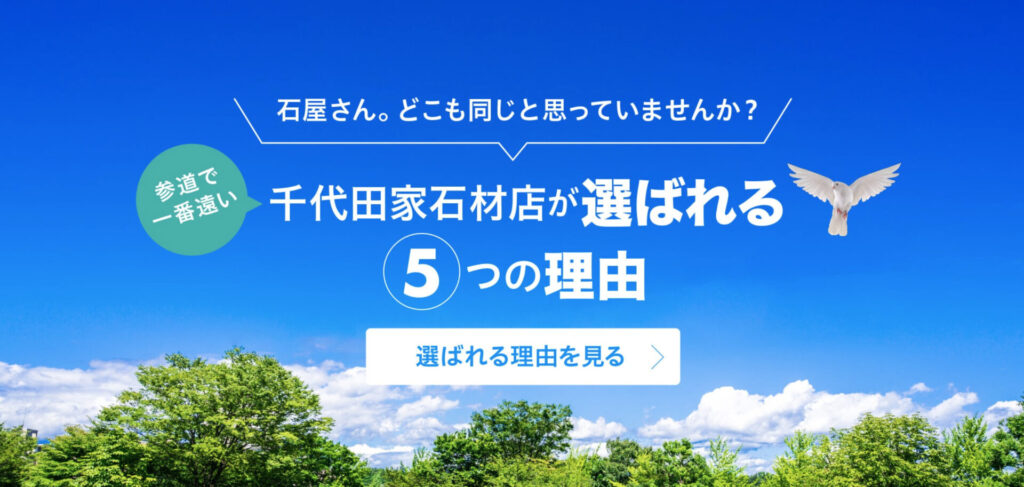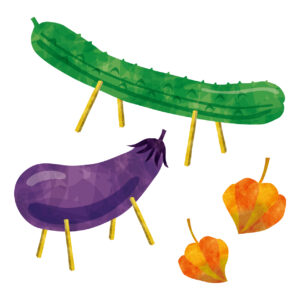【お彼岸に学ぶ】心を軽くする仏教の知恵「六波羅蜜」|現代人にも役立つ暮らしの習慣
お彼岸というと、「お墓参りに行く時期」というイメージを持つ方が多いかもしれません。もちろん、ご先祖さまに手を合わせる大切な習慣ですが、実はそれだけではありません。
お彼岸の背景には、仏教の教えである「六波羅蜜(ろくはらみつ)」という考え方があり、これは“心を整える6つの習慣”とも言えるものです。
少し聞き慣れない言葉かもしれませんが、内容はとても身近。たとえば「人に優しくする」「感謝を伝える」「小さな努力を続ける」といった、普段の生活にも役立つヒントがたくさんつまっています。
お彼岸は、ご先祖さまを偲ぶと同時に、自分自身の心を見つめ直すきっかけでもあるのです。この記事では、六波羅蜜の意味と、その教えを私たちの日常にどう生かせるのかを、やさしくご紹介していきます。

目次
●六波羅蜜とは?
「六波羅蜜(ろくはらみつ)」という言葉を聞いたことはありますか?
これは仏教で説かれている 悟りに至るための6つの修行のこと を指し、菩薩(悟りを求め、他者を助ける存在)が歩むべき道とも言われています。
仏教では、私たちが今生きている迷いや苦しみの世界を「此岸(しがん)」、その向こうにある悟りや安らぎの境地を「彼岸(ひがん)」と呼びます。
そして「六波羅蜜」とは、まるで 此岸から彼岸へ渡るための船 のような役割を持つ修行の道筋です。実際、「波羅蜜」という言葉自体に「彼岸へ到る」という意味が込められているんですよ。
とはいえ、六波羅蜜はお坊さんだけが行う特別な修行ではありません。
「布施(ふせ)=誰かにやさしくすること」や「忍辱(にんにく)=ついカッとなる心を抑えること」など、日常の中で自然に実践できるものばかり。
形式的に難しいことをしなくても、普段の生活の中に取り入れられる「心の習慣」として役立つ教えなのです。
お彼岸の期間には「先祖供養をしながら自分の心も見つめ直す」という意味合いがありますが、その際の 心の指針として六波羅蜜を意識すると、より深い気持ちでお彼岸を過ごすことができる でしょう。

①布施(ふせ)|与えることで心を豊かに
・仏教的な意味
仏教の教えにある「布施」とは、見返りを求めずに 物・知恵・労力を他者に与えること を指します。単にお金や物を寄付するだけでなく、心からの思いやりを込めて施すことが大切です。これによって、自分の中にある「執着」を手放し、利他の心を育てていくのが布施の本来の目的です。
・こんな場面で活かせます
現代の日常生活で考えると、布施はとても身近なところにあります。たとえば――
- 電車やバスで席を譲る
- 家族や友人に「ありがとう」と言葉を伝える
- 困っている人にちょっとした手を差し伸べる
- 自分が知っている知識や経験をシェアする
こうした小さな行いも立派な布施です。誰かに優しさを分け与えると、自分の心も自然と温かく、豊かになっていくのを感じられるはずです。
お彼岸の時期は特に「布施」を意識してみると良いでしょう。身近な人にちょっとした思いやりを向けるだけで、自分自身の心も落ち着き、日々の生活にやさしい彩りが加わります。
②持戒(じかい)|ルールを守ることで心を整える
・仏教的な意味
仏教の「持戒」とは、戒律(かいりつ)=ルールを守ること を意味します。これは「欲望や衝動に振り回されないように、自分を律する」ための実践です。お酒を慎む、嘘をつかない、他人を傷つけない…といった基本的な戒めを守ることで、心を清らかに保ち、安定へと導いてくれるのです。
・こんな場面で活かせます
現代の日常生活に置き換えると、とても身近な行動の中に「持戒」があります。
- 約束の時間をきちんと守る
- 交通ルールを守って安全に過ごす
- SNSで誰かを傷つける言葉を投稿しない
こうした小さなことも「ルールを守る」という持戒の実践です。社会の中で守るべき約束事を大切にすることは、自分自身の心を整え、周りとの関係を良好にする大切な基盤になります。
お彼岸の時期は「ちょっとだけ丁寧に約束を守ってみよう」と意識してみるのも良いでしょう。日常の中での持戒は、私たちに安心感と落ち着きを与えてくれます。
③忍辱(にんにく)|耐え忍ぶ力を育てる
・仏教的な意味
「忍辱(にんにく)」とは、困難や屈辱に耐え、怒りや憎しみの感情を抑えること を修行とする教えです。仏教では、苦しい状況に出会ったときに感情のままに反応せず、心を落ち着けて受け止めることが悟りに近づく道だとされています。
・こんな場面で活かせます
現代の生活でも、この「忍辱」は大切なヒントになります。
- 職場で理不尽なことを言われても、すぐに言い返さず冷静に対応する
- 家庭や人間関係の中でイライラしても、深呼吸して気持ちを落ち着ける
- ネガティブな言葉に過剰反応せず、受け流す
こうした「感情をコントロールする力」は、まさに現代版の忍辱です。怒りや不満に流されると自分も疲れてしまいますが、一呼吸おいて落ち着いて対応できれば、結果的に自分の心も守ることにつながります。
お彼岸の時期には、普段より少しだけ「怒らない工夫」を意識してみましょう。そうすることで、心に余裕が生まれ、人との関わりも柔らかくなるはずです。
➃精進(しょうじん)|努力を積み重ねる姿勢
・仏教的な意味
「精進(しょうじん)」とは、怠けることなく、正しい行いを継続していくこと を意味します。仏教では、一度や二度の善行だけでなく、日々の小さな努力を重ねていくことが悟りの道につながると説かれています。
・こんな場面で活かせます
現代に置きかえると、精進とは「コツコツ続ける力」。
- 勉強や仕事を毎日少しずつ積み重ねる
- 健康のために運動や食生活を整える
- 感謝の気持ちを忘れずに習慣化する
こうした 小さな努力の積み重ね が、やがて自分自身を大きく変えていきます。
お彼岸の時期には、「何かひとつ続けてみよう」と決めるのもおすすめです。例えば、1日5分の読書やストレッチでも立派な精進。大切なのは完璧さではなく、「続けよう」という姿勢そのものです。
⑤禅定(ぜんじょう)|心を静めて集中する
・仏教的な意味
「禅定(ぜんじょう)」とは、瞑想や坐禅を通じて心を落ち着け、乱れから解放される修行 のことです。仏教では、心が常に欲望や不安で揺れ動いている状態を「散乱」と呼びます。禅定はその散乱を鎮め、集中力と心の安定を養う大切な実践です。
・こんな場面で活かせます
現代に置きかえると、禅定は「心のリセット」にあたります。
- マインドフルネス瞑想を取り入れてみる
- 1日数分、深呼吸をして気持ちを整える
- スマホやパソコンから少し離れて、デジタルデトックスをする
このように 静かな時間を意識的につくること で、頭の中の雑念がクリアになり、心が安定します。仕事や人間関係のストレスを抱えがちな現代人にとって、禅定は「心の充電時間」とも言えるでしょう。
お彼岸は、普段の忙しさから一歩離れ、心を見つめ直す絶好のタイミングです。数分の静かなひとときでも、自分を整える大きな一歩になります。
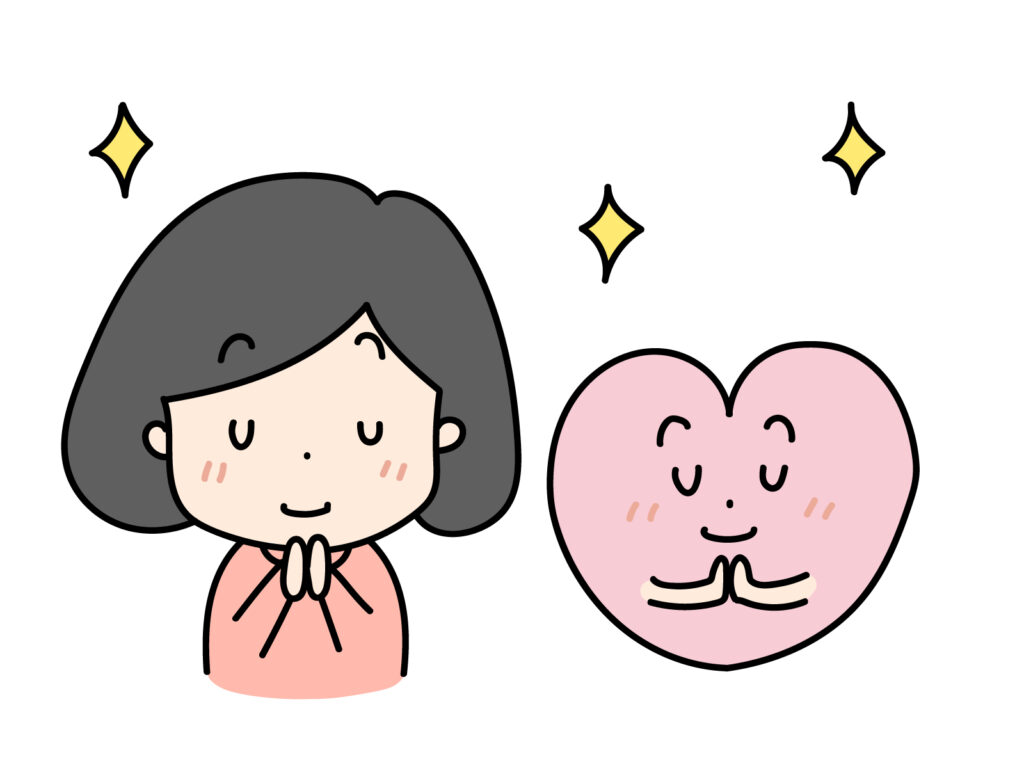
⑥智慧(ちえ)|物事を正しく見極める力
・仏教的な意味
「智慧(ちえ)」とは、仏教において 真理を理解し、物事の本質を正しく見極める力 を意味します。単なる知識の多さではなく、迷いや無知を超えて、正しい判断を下す力として重視されています。六波羅蜜の最後に位置づけられ、他の修行を支える大切な柱でもあります。
・こんな場面で活かせます
現代に置きかえると、智慧とは「自分の頭で考え、選び取る力」。
- インターネットやSNSの情報を鵜呑みにせず、正しいかどうかを自分で調べて判断する
- 人の立場や価値観の違いを尊重し、多角的に物事を考える
- 感情や先入観に流されず、冷静に物事の本質を見抜く
こうした日々の姿勢が「智慧」を育みます。
お彼岸の時期には「まず疑ってみる」「いろんな視点を持つ」と意識するだけでも立派な智慧の実践になります。

●六波羅蜜を現代に生かすには
六波羅蜜というと、少し難しい修行のように感じるかもしれません。でも実際には、特別な修行や厳しい戒律を守ることだけが大切なのではなく、日常の小さな行動の積み重ねが六波羅蜜の実践になる といわれています。
たとえば――
- お墓や家の掃除をして環境を整える(精進・持戒)
- 家族や友人に「ありがとう」と感謝を伝える(布施)
- 誰かが困っていたら声をかける、人に優しくする(忍辱・布施)
- スマホを置いて、静かにお茶を飲む時間をつくる(禅定)
こうした行為そのものが、心を軽くし、穏やかにしてくれます。
お彼岸は、ただ先祖を供養するだけでなく、自分の心を見つめ直すきっかけ にもなる大切な期間です。このタイミングで六波羅蜜の考え方を日常に取り入れてみると、毎日の暮らしが少しずつ優しく、そして心豊かに変わっていくはずです。
六波羅蜜は、古くからお彼岸の時期に意識されてきた仏教の知恵ですが、決して昔の人だけのものではありません。むしろ今を生きる私たちにこそ、人間関係や心の健康を整えるヒントになる教えです。
「与える(布施)」「守る(持戒)」「耐える(忍辱)」「続ける(精進)」「静める(禅定)」「見極める(智慧)」――この6つを一度に完璧に行う必要はありません。ちょっとした場面で思い出して、できることから少しずつ取り入れてみる。それだけで、毎日の心の持ち方が変わり、日々がより穏やかで豊かに感じられるはずです。
お彼岸は、ご先祖さまへの感謝とともに、自分の心を整える大切な機会。ぜひこの機会に、六波羅蜜の教えを暮らしの中で実践してみませんか?
| 六波羅蜜 | 仏教的な意味 | 現代での実践例 |
|---|---|---|
| 布施(ふせ) 与えることで心を豊かに |
見返りを求めずに施す | ・電車で席を譲る ・「ありがとう」を伝える ・知識や時間を分け合う |
| 持戒(じかい) ルールを守ることで心を整える |
戒律を守り、欲望に流されない |
・時間や約束を守る ・交通ルールを守る ・SNSで人を傷つけない |
| 忍辱(にんにく) 耐え忍ぶ力を育てる |
困難に耐え、怒りを抑える | ・ストレスに冷静に対応する ・相手の言葉に過剰反応しない ・感情をコントロールする |
| 精進(しょうじん) 努力を積み重ねる姿勢 |
怠けずに正しい行いを続ける | ・毎日の勉強や仕事をコツコツ続ける ・運動や健康習慣を取り入れる ・感謝を日々言葉にする |
| 禅定(ぜんじょう) 心を静めて集中する |
瞑想で心を整える | ・深呼吸やマインドフルネス ・デジタルデトックス ・静かな時間を大切にする |
| 智慧(ちえ) 物事を正しく見極める力 |
真理を理解し正しい判断を下す |
・情報を鵜呑みにせず調べる |
●おわりに
お彼岸というと「お墓参りをする期間」というイメージが強いですが、その背景には六波羅蜜という“心を整えるための知恵”があることをご紹介しました。
与えること、守ること、耐えること、続けること、静めること、そして見極めること。どれも特別な修行ではなく、日常の中で少しずつ実践できる習慣です。たとえば「ありがとう」と伝えることや、家の掃除を丁寧にすることも立派な六波羅蜜の実践なのです。
お彼岸の時期は、自然と家族やご先祖さまを想う時間が増えます。この機会に、自分自身の心を振り返る時間をつくってみませんか。六波羅蜜は私たちの暮らしに寄り添い、心を軽くしてくれる道しるべになります。どうぞ、ご自身のペースでできることから取り入れてみてくださいね。
監修者情報

渡辺裕
(わたなべゆたか)
1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。実家が石材店のため、小さい頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。
有限会社 千代田家石材店/代表取締役
一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00
一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級
一般社団法人 日本看取り士会/看取り士
一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士
ーお墓に関するご相談ならぜひ千代田家石材店にー
当社は大正8年に八柱霊園の参道に創業してから100余年。
千代田家石材店は、お客様に寄り添ったご提案・ご法要・お墓参りのお手伝いをさせて頂いています。
埼玉県さいたま市の岩槻北稜霊園のほか、埼玉、茨城、千葉県内に多数お取り扱いの霊園がございます。
ご埋葬やお墓の購入、お墓のリフォームなど、お墓やご法要に関することでしたら、何でもご相談ください!
有限会社 千代田家石材店
住所:〒270-2253 千葉県松戸市7-450(八柱霊園 中参道)
営業時間:8:00〜19:00(土日祝日営業)
店舗定休日:火曜(祝日・お盆・お彼岸・年末年始を除く)
※各霊園のご案内は随時行っております。
TEL/FAX:047-387-2929/047-389-0088
HP:https://chiyodaya.co.jp/
ーその他の霊園ー
【2023年11月23日 新区画オープン】