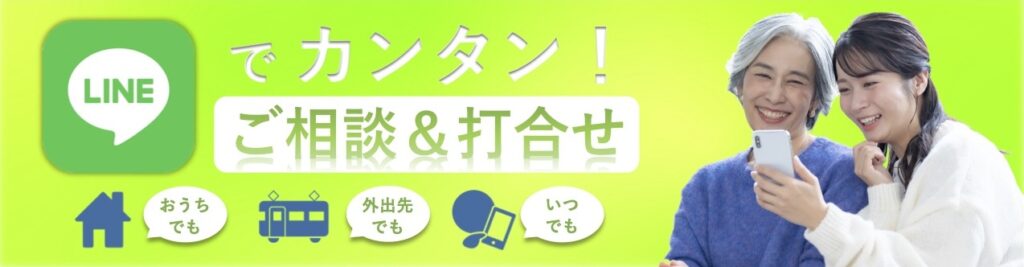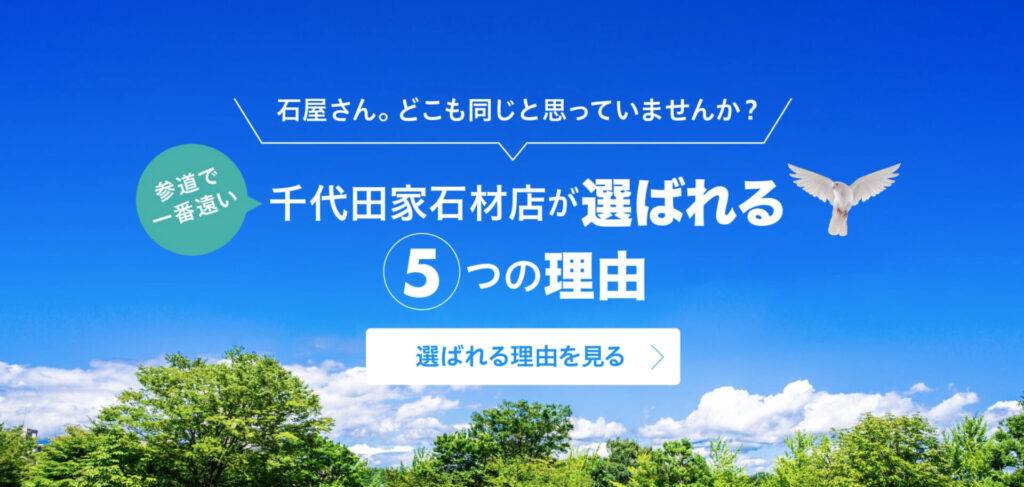墓じまいが増えている理由とは?手続きの流れ・供養のかたち・価値観の変化をわかりやすく解説
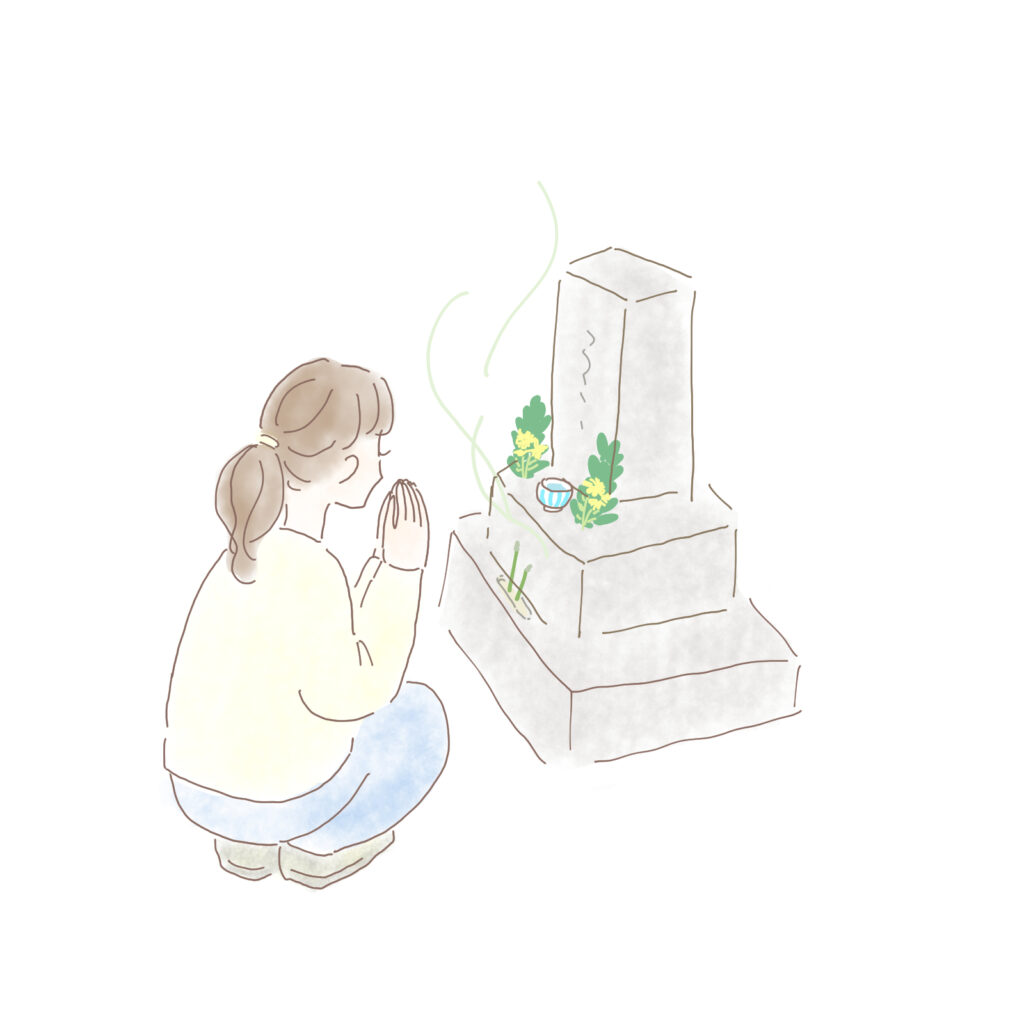
近年、「お墓じまい」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
お墓じまいとは、ご先祖さまが眠るお墓を整理・撤去し、遺骨を別の場所へ移すことを指します。
「遠方にあるお墓を管理するのが難しくなってきた」
「後継ぎがいないので今のうちに整理しておきたい」
「経済的な負担を減らしたい」
こうした理由から、お墓じまいを検討される方が増えています。
とはいえ、「何から始めたらいいの?」「費用はどのくらい?」「親族にどう説明すれば…」といった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
このブログでは、お墓じまいの基本的な流れや費用、選ばれる背景、注意すべきポイントなどをわかりやすくご紹介します。
ご自身やご家族にとって、よりよい供養のかたちを考えるきっかけになれば幸いです。
目次
○墓じまいとは
「墓じまい」とは、現在あるお墓を撤去し、そこに納められているご遺骨を別の場所へ移すことを指します。
ただ単にお墓を壊すということではなく、これまでの供養に感謝しながら、より無理のないかたちで大切なご先祖さまをお守りしていくための選択です。
たとえば、お墓が遠方にあってなかなかお参りに行けなかったり、お墓を継ぐ人がいなかったり、経済的な事情で維持が難しくなった場合などに、「墓じまい」を選ばれる方が増えています。
・墓じまいの一般的な流れ
お墓じまいは、いくつかの段階を踏んで進めていきます。以下は一般的な流れの一例です。
- 親族との相談・合意
まずは、親族や関係者とよく話し合い、墓じまいについて理解と合意を得ることが大切です。 - ご遺骨の移転先(改葬先)を決める
永代供養墓、樹木葬、納骨堂など、供養のかたちはさまざまです。家族の考えに合った方法を選びましょう。 - 改葬許可申請の手続きを行う
現在お墓がある市区町村の役所で「改葬許可証」を取得します。 - 閉眼供養・魂抜き(お性根抜き)を行う
お墓を撤去する前に、お寺さまにお願いして仏さまの魂を抜いていただきます。 - 墓石の撤去工事を依頼する
石材店に依頼し、お墓を丁寧に撤去してもらいます。 - 新しい供養先へご遺骨を移す(納骨)
改葬先にて納骨を行い、新しいかたちでご供養を続けていきます。
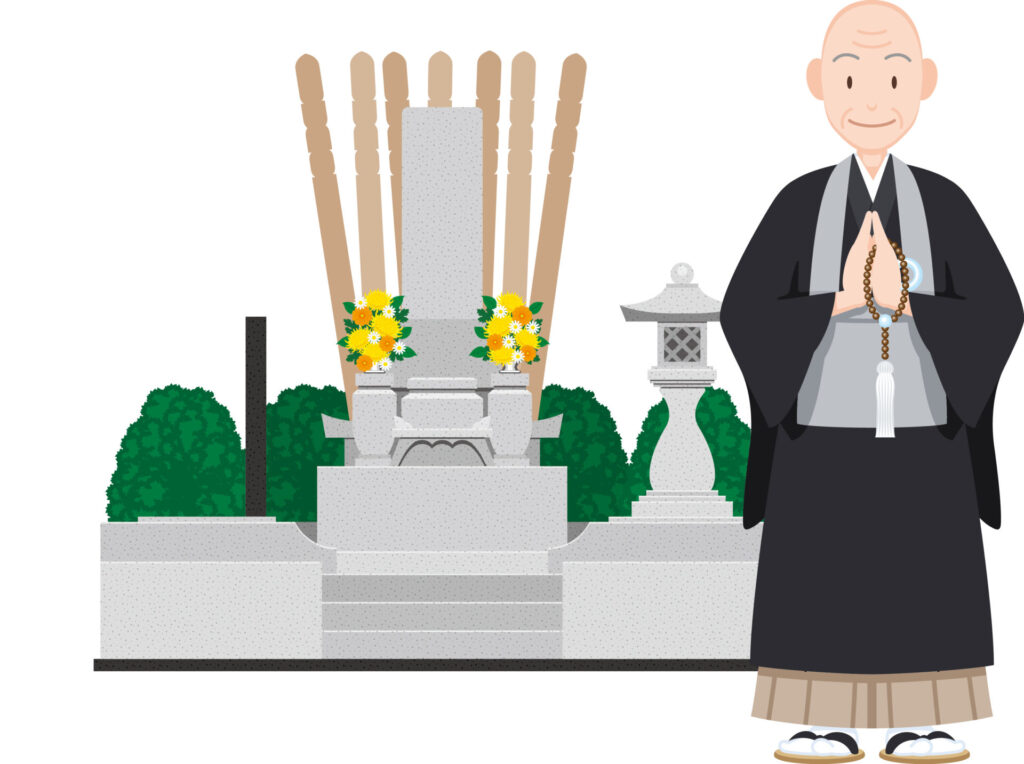
・墓じまいに必要な書類と関係機関
墓じまいには、いくつかの公的な手続きが必要です。主に以下の書類を準備することになります。
- 改葬許可申請書
今あるお墓のある市区町村の役所に提出します。 - 埋蔵証明書(または受入証明書)
遺骨を移す先の施設(お寺や納骨堂など)から発行されます。 - 改葬許可証
申請が受理されると、役所から発行されます。これがないとご遺骨を移動することができません。
必要書類の内容や手続きは地域によって異なる場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。
また、書類の準備や改葬先とのやり取りに不安がある方は、石材店や専門業者に相談するのも一つの方法です。
○墓じまいが増えている理由|現代社会が墓じまいを選ぶ背景
ひと昔前までは、「お墓は代々受け継いでいくもの」という考え方が一般的でした。
しかし、近年ではその価値観が少しずつ変わりつつあり、「墓じまい」を選択するご家庭が増えています。
その背景には、現代ならではの社会的な変化が大きく関わっています。
家族構造の変化
近年、日本の家族のかたちは大きく変わってきています。
特に戦後の高度経済成長期を経て、経済や社会、文化などさまざまな面で変化が進み、昔ながらの「家族のあり方」も少しずつ変わってきました。
・大家族から核家族へ
かつての日本では、祖父母・両親・子どもたちが一緒に暮らす「大家族」が一般的でした。
家族の中にお墓の管理や供養を引き受ける人が複数いたため、代々しっかりとお墓が守られてきました。
しかし現在では、親と子、あるいは夫婦だけで暮らす「核家族」が主流になりつつあります。
家族の人数が減ることで、お墓を守る役割を担う人も限られてしまい、結果として「墓じまい」を考えるご家庭が増えてきているのです。
・子どもの数の減少
日本の少子化も、お墓の継承に影響を与えている大きな要因です。
子どもが少なくなれば、それだけ将来お墓を引き継ぐ人も少なくなります。
「誰が継ぐのか分からない」「子どもに負担をかけたくない」と感じ、今のうちにお墓の整理を検討される方も多くいらっしゃいます。
・都市部への人口集中
仕事や進学のために、多くの人が地方から都市部へ移り住むようになりました。
この結果、「実家のお墓が遠くて、なかなかお参りに行けない」と悩む方が増えています。
年に数回の帰省すら難しいというご家庭もあり、これもまた墓じまいの背景の一つとなっています。
・単身赴任や留学による家族の分散
最近では、仕事の都合での単身赴任や、子どもの海外留学など、家族がそれぞれ別々の場所で暮らすケースも増えてきました。
こうした生活スタイルの変化によって、家族全体でお墓を守るという意識やつながりが希薄になってしまうこともあります。

経済的な問題
お墓を維持していくには、さまざまな費用がかかります。
特に近年では、こうしたお墓に関わる経費の増加が、ご家族にとって大きな負担となってきています。
「お墓を守りたい気持ちはあるけれど、現実的に難しい…」という声が増えている背景には、現代社会ならではの事情があります。
・墓地の購入費用の高騰
まず大きな要因のひとつが、墓地の購入費用の上昇です。
特に都市部では土地の価格が年々上がっており、その影響は霊園や墓地の販売価格にも表れています。
交通の便が良い場所や、設備の整った人気の霊園ほど価格が高く、なかには数百万円単位の費用が必要になることもあります。
また、都市部では新たな霊園を開発する土地も限られており、需要と供給のバランスから今後も価格が高止まりする傾向があるとされています。
・維持管理にかかる年間の費用
お墓は建てて終わりではなく、その後も毎年の維持費がかかります。
たとえば霊園の管理費や清掃費、墓石の劣化を防ぐメンテナンス代などが挙げられます。
風雨や気温差によって墓石が傷んでしまった場合には、修理や補修が必要になることもあり、その都度想定外の出費が発生することもあります。
また、季節ごとの供花やお供え物の準備など、細かな出費も積み重なると決して小さな負担ではありません。
・供養に関するさまざまな費用
お墓を守っていくうえでは、法要やお盆、お彼岸といった年中行事に関する費用も必要です。
お寺さまへのお布施、供物の準備、仏具の買い替えなど、毎年のようにかかる供養の費用は、家計への影響も小さくありません。
特に最近では、こうした行事にきちんと対応しようとするご家庭ほど、「お墓を守る=経済的な負担」と感じることも増えているようです。
・社会的な背景
日本全体の経済状況もまた、お墓にかかる費用負担を重くしている一因です。
コロナ禍による収入減や物価上昇などの影響で、「毎年続く固定的な出費が厳しい」と感じるご家庭も増えています。
そうした中、「この先も安心して供養を続けられる方法はないか?」と考え、墓じまいを前向きな選択肢として検討される方が増えているのです。

価値観の多様化
近年、日本では「供養のかたち」そのものに対する考え方が大きく広がってきています。
「自然の中で眠りたい」「家族に負担をかけたくない」「宗教にとらわれず、自分らしく供養されたい」
そうした想いを持つ方が増えるなかで、従来のお墓にこだわらない新しい供養方法が注目されています。
・散骨という選択肢
自然に還ることを願い、海や山などにご遺骨を撒く「散骨」も人気が高まっています。
お墓という“場所”を持たないこの方法は、自然との一体感を大切にしたい方や、形式にとらわれたくない方に選ばれています。
最近では、海への「海洋散骨」や、山林への「山散骨」など、多様なプランが用意されており、専門の業者に依頼することで安心して行うことができます。
・自然葬の広がり
自然葬は、森林や草花に囲まれた自然の中に遺骨を埋葬する方法です。
自然との共生を大切にし、「環境に優しい供養を選びたい」と考える方から支持を集めています。
墓石ではなく、木や花を墓標とするスタイルも多く、「自然の中で静かに眠りたい」という故人の想いをかたちにする手段として注目されています。
・共同墓という安心のかたち
経済的な理由や「家族に負担をかけたくない」という考えから、「共同墓」を選ぶ方も増えています。
これは、複数の方とひとつのお墓を共有するスタイルで、永代供養が前提となっているケースが多いため、後継ぎがいなくても安心です。
中には、生前から親しい友人同士で共同墓を選ぶケースもあり、「人生の最期も一緒に」という想いが込められています。
・死生観や墓所観の変化
こうした供養方法の多様化の背景には、日本人の「死生観」や「お墓に対する意識」の変化があります。
グローバル化が進み、さまざまな文化や価値観に触れる機会が増えるなかで、「亡くなったあとも自分らしくありたい」と考える方が増えています。
特に若い世代では、「家族墓」や「代々受け継ぐお墓」といった伝統的なスタイルにこだわらない考え方が広がってきました。
核家族化や単身世帯の増加、地方から都市への移動といった社会の変化が、その背景にあります。
・墓は“思い出の場所”へ
最近では、「お墓=供養の場」というだけでなく、「故人との思い出を共有する場所」としての役割も注目されています。
家族や友人が気軽に集まり、故人との思い出を語り合える。そんなお墓のあり方を望む方も増えています。
形式にとらわれず、心を通わせる時間や空間を大切にする。
それも、今の時代に合った新しい供養のスタイルのひとつなのかもしれません。
このように、供養やお墓に対する考え方は、時代とともに少しずつ変化しています。
大切なのは、「何を選ぶか」ではなく、「どう想いを込めるか」。
それぞれのご家庭やご本人の価値観に合った、心から納得できるかたちで、故人を偲ぶことが何より大切だといえるでしょう。
○墓じまい後の遺骨はどうする?選べる供養の方法
墓じまいを行ったあとは、ご遺骨をどこにどう納めるかという「新しい供養のかたち」を考えることになります。
近年では、従来のお墓だけでなく、ライフスタイルや価値観に合わせた多様な供養方法が選ばれるようになってきました。
ここでは、代表的な供養の方法をご紹介します。
・永代供養墓(えいたいくようぼ)
永代供養墓とは、寺院や霊園がご遺骨をお預かりし、供養から管理までを永続的に行ってくれるお墓のことです。
ご家族に代わってお寺や霊園が供養してくれるため、「後継ぎがいない」「子どもに負担をかけたくない」とお考えの方に選ばれています。
個別に納骨されるタイプや、他の方と一緒に埋葬される合祀(ごうし)タイプなど、形式は施設によってさまざまです。
・樹木葬(じゅもくそう)
自然の中で眠ることを希望される方には、樹木葬という方法もあります。
これは墓石の代わりに樹木や草花を墓標とし、自然と共に眠る新しい供養のスタイルです。
「自然に還りたい」「シンプルに供養してほしい」といった思いを持つ方に人気で、宗教や宗派にとらわれない自由なお墓として注目されています。
場所によっては、森の中や専用の庭園で行われることもあります。
・納骨堂(のうこつどう)
納骨堂は、ご遺骨を建物の中に安置する室内型のお墓です。
空調やセキュリティが整っており、天候に左右されずにお参りできるのが特徴です。
都市部を中心に増えており、「自宅から通いやすい」「高齢になっても無理なくお参りできる」といった理由から選ばれる方も多いです。
最近では、カードキーや自動搬送システムを導入している現代的な納骨堂もあります。
・手元供養や散骨という選択肢も
ご遺骨を身近に置いて供養したいという方には、「手元供養」という方法もあります。
専用の骨壺やアクセサリーに一部のご遺骨を納め、ご自宅で供養するスタイルです。
仏壇やお墓にこだわらず、ご自身の想いに合った形で故人を偲ぶことができます。
また、海や山などにご遺骨を撒く「散骨」も、近年選ばれる方が増えています。
自然に還ることを願う方にとっては、自由で心に寄り添った供養の方法といえるでしょう。
ただし、散骨には一定のルールや配慮も必要となるため、専門業者に相談するのがおすすめです。
このように、墓じまいのあとにはさまざまな供養の選択肢があります。
大切なのは、ご本人やご家族が「これでよかった」と心から思える方法を選ぶこと。
迷われたときには、石材店や寺院などの専門家に相談することで、安心して次の一歩を踏み出せるはずです。
○墓じまいで後悔しないために注意すべきポイント
お墓じまいは、ご先祖さまを大切に想うからこその大きな決断です。
その一方で、「あとでトラブルになってしまった…」「もう少し考えておけばよかった…」という後悔の声も耳にします。
ここでは、墓じまいを安心して進めるために、事前に気をつけておきたいポイントをご紹介します。
・親族との話し合いを大切に
墓じまいを進めるうえで、もっとも大切なのが「ご親族との話し合い」です。
お墓にはご家族それぞれの思い入れがありますので、「勝手に決められてしまった」と感じる方がいると、後々のトラブルにつながることもあります。
できるだけ早い段階で事情や気持ちを丁寧に伝え、納得してもらったうえで進めることが、何より大切です。
可能であれば家族会議を開いたり、法事などの機会に相談してみるのもよいでしょう。
・改葬許可証は必ず取得を
ご遺骨を別の場所に移す際には、市区町村の役所から「改葬許可証」を取得する必要があります。
この許可証がないと、正式にご遺骨を移動することができません。
申請には、現在のお墓があるお寺や霊園からの「埋蔵証明書」や、移転先の施設が発行する「受け入れ証明書」などが必要になります。
地域によって手続きが異なる場合もありますので、あらかじめ役所や石材店に相談して確認しておくと安心です。
・撤去業者と供養先は信頼できるところを
墓じまいには、墓石の撤去や新たな供養先の手配といった実務も伴います。
特に石材店や撤去業者の対応や費用、供養先の対応内容などは事前によく調べて、信頼できる業者を選ぶことが大切です。
以下のような点をチェックすると良いでしょう:
- 墓石の撤去費用に含まれる内容は明確か?(例:更地に戻すまで含まれるか)
- 供養先は永代にわたって対応してくれるか?
- 宗教・宗派の対応可否はどうか?
- 実績や口コミ、対応の丁寧さ
また、不明点があれば遠慮せずに質問することも大切です。「ここにお願いしてよかった」と思える相手に任せることで、安心して進められるはずです。
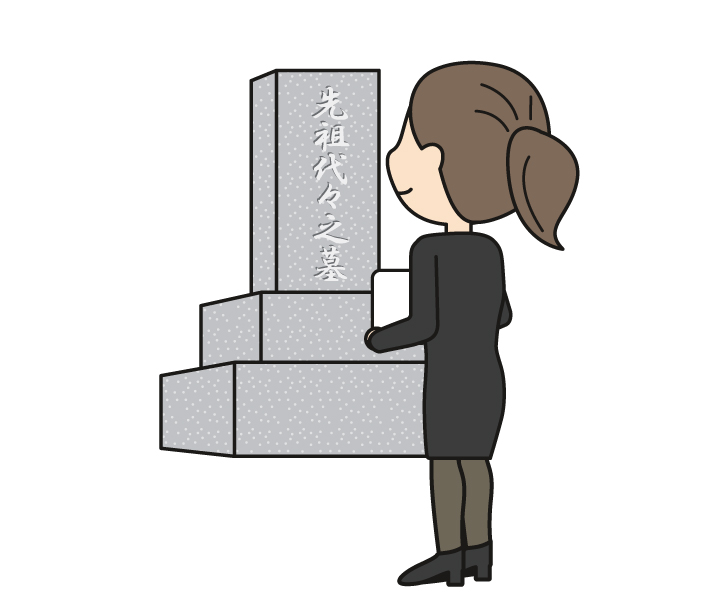
おわりに
墓じまいの増加背景は、近年の日本の社会的、経済的、文化的変動を反映しています。家族構造の変化や経済的な負担、そして新しい価値観や死生観の変化は、伝統的な家族墓の形式を見直す動きを促進しています。
特に、散骨や自然葬などの新しい供養の方法の受容は、私たちの死後の考え方や、故人との関わり方に新しい風をもたらしています。
今後も社会は変わり続けるでしょうが、大切なのは故人を偲ぶ気持ちと、遺族の心の平和を守ることです。多様な供養の形式が存在することは、それぞれの家族が自分たちに合った方法を選べる豊かさを意味します。伝統も新しいスタイルも、それぞれの背景や価値があります。大切なのは、亡くなった人を思う心と、その人の存在をどう記憶していくかにあるのかもしれません。
監修者情報

渡辺裕
(わたなべゆたか)
1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。実家が石材店のため、小さい頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。
有限会社 千代田家石材店/代表取締役
一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00
一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級
一般社団法人 日本看取り士会/看取り士
一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士
ーお墓に関するご相談ならぜひ千代田家石材店にー
当社は大正8年に八柱霊園の参道に創業してから100余年。
千代田家石材店は、お客様に寄り添ったご提案・ご法要・お墓参りのお手伝いをさせて頂いています。
埼玉県さいたま市の岩槻北稜霊園のほか、埼玉、茨城、千葉県内に多数お取り扱いの霊園がございます。
ご埋葬やお墓の購入、お墓のリフォームなど、お墓やご法要に関することでしたら、何でもご相談ください!
有限会社 千代田家石材店
住所:〒270-2253 千葉県松戸市7-450(八柱霊園 中参道)
営業時間:8:00〜19:00(土日祝日営業)
店舗定休日:火曜(祝日・お盆・お彼岸・年末年始を除く)
※各霊園のご案内は随時行っております。
TEL/FAX:047-387-2929/047-389-0088
HP:https://chiyodaya.co.jp/
ーその他の霊園ー
【2023年11月23日 新区画オープン】